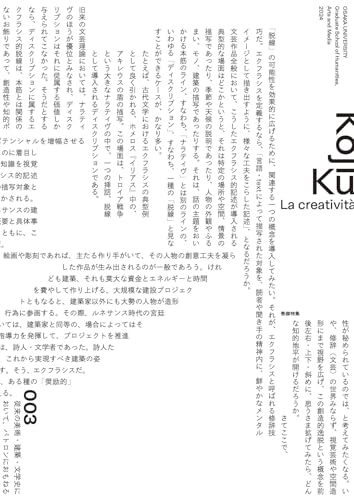紹介
大阪大学文学研究科アート・メディア論研究室が発行する本誌『Arts and Media』は、アートとメディアの原初の関係に改めて注目し、芸術をもう一度、情報伝達の手段として見てみたい、そんな熱望から生まれた雑誌である。あるいは逆に、現在、情報伝達のツールとして生まれ、活用されている様々な手段が、今まさにアートへと変貌しつつあるその瞬間を切り取ってみたい。
収録される論考は、映画や写真、絵画、建築、文学、マンガ、新聞・ラジオ、演劇、博物館学などなど、実に多彩だ。この「祝祭的な混沌」が生み出すジャンル不明性こそは、ただ本研究室にのみ醸成可能な知的テンションであると自負するものである。
遺伝子の多様性が生命の安全装置として機能するように、我々は文化の多様性を保つことこそが、現代社会に対するある種のセーフティネットになるものと心から信じている。 文だの理だのといった狭隘な専門跼蹐の殻を打ち破り、百学連環の知の饗宴をとくと愉しんでいただきたい。
編集長 桑木野幸司
目次
[追悼]
古後奈緒子|市川明先生と演劇のカレイドスコープ──手がかりとしての壁際のテクスト
[巻頭言]
東 志保
[巻頭特集]
「脱線」の魅惑/知の視覚
岡北一孝|イタリア・ルネサンスの建築エクフラシス:建築・文学・美術を統合的に考える
関俣賢一|ラブレーにおける〈記憶・脱線・発想〉考察のために──『第三の書』を中心として
[論文]
鈴木聖子|音楽芸能の記録における音と映像の関係──日本ビクターの音響映像メディアのアンソロジー(中編)
柴尾万葉|ピピロッティ・リストの映像作品におけるエレーヌ・シクスーの思想との共通性
武本彩子|ギー・ドゥボールの初期映画におけるニュース映画の「転用」
城 直子|近世カトマンズ旧市街におけるクマリの館と山車巡行の役割
片岡浪秀|放送界と石井光次郎(戦前〜占領期篇)──NHK会長人事への介入と朝日新聞の目論見
[研究ノート]
古後奈緒子|ベルリン王立歌劇場バレエの組織と演目:舞踊史の隠れた位相としての(長い)十九世紀バレエ
橋本知子|『家からの手紙』におけるニューヨークの表象──ディアスポラの観点から
[インタビュー]
奥野晶子|コンクリート・ポエトリーの系譜──大谷陽一郎氏インタビュー
野尻倫世|「役者」を経験した落語家──新人落語家の挑戦
[エッセイ]
河﨑伊吹|記憶の町を編み上げる──みなとメディアミュージアム2024での実践から
[再録]
「退職記念:市川明教授」
※本誌は造本設計のコンセプトに基づき、意図的に一部のページを落丁させております。落丁したページは別冊「落丁本」に纏められております。
前書きなど
二〇二四年四月で、アート・メディア論コースが発足してから一七年目、『Arts and Media』が発刊してから一五年目となります。この間、私が知る限りでも多くの変化がありました。羽ばたいていく修了生と新しい風を吹き込んでくれる新入生による毎年の「新陳代謝」はさることながら、研究科再編による芸術学専攻への異動、コースの創設にご尽力くださった先生方の退官など、アート・メディア論コースはこの一七年間に数多くの経験を積んできました。
それでも失われないのは、所属する学生たちの多様な関心と属性、その「雑多さ」が否定されない自由な雰囲気だと思います。私が本コースに着任した当初、抱いた印象は、正にモザイクでした。バラバラなのに妙に調和がとれていて、みな糸がきれた凧のように飛んでいってしまいそうなのに最終的には戻ってくる。今号の巻頭特集のテーマの「脱線」を象徴するようなコースのように思います。
この独特の雰囲気は、創設に関わられた先生方の寛容さによるものと思います。その創設者の一人であり、本誌の立役者である市川明先生が、一月八日、逝去されました。私は、先生とは、一度、学生たちと一緒に食事をとったのみの交流しかありませんが、初対面ながら、市川先生の朗らかで熱いお人柄にすっかり魅了されてしまいました。前衛的なデザインも本誌の魅力ですが、それも松本工房さんを紹介してくださった市川先生のご人脈によるものです。本誌に継続的に寄せてくださったブレヒト論が読めなくなるのは淋しいですが、自由な精神に満ち満ちた、開かれた雑誌であり続けたいと思います。(東 志保)