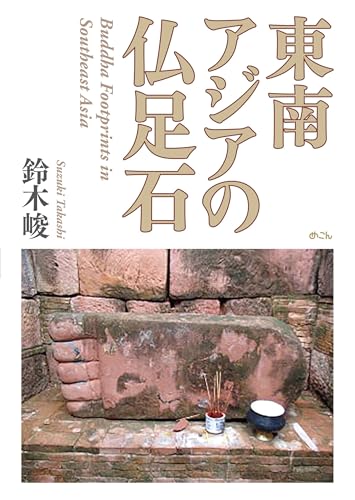目次
第1章 東南アジアの仏足石概論
1. 東南アジア各地の仏足石
2. 2種類の仏足石
3. シュリヴィジャヤと大乗仏教
4. 古い仏足石
5. シュリヴィジャヤ時代の仏足石
6. 法顕の耶婆提
7. モン族と仏足石
8. スコータイ・アユタヤ時代の仏足石
9. マレー半島の仏足石
10.絢爛豪華な108紋仏足石
第2章 マレー半島の仏足石と通商ルートの歴史
1. 初期の素朴な仏足石
2. 足型の仏足石に
3. 深彫り、装飾化していく仏足石
4. クラ地峡の通商ルートからタクアパルートへの転換
5. さまざまなタイプの仏足石
6. 108吉祥紋の大型仏足石
第3章 仏足石を訪ねて
1. サムイ島
2.サティンプラ
3. プーケット・タクアパ周辺
4. ビエンチャン
5. ナコーンシータムマラートでの国際セミナーとスコータイ
6. イサーン(タイ東北部)
7.シーテープとサラブリー
8.ペッチャブリー、フアヒン方面(旧羅越)
9.ウボンラーチャターニー、パークセー、ワット・プー、カンボジア
10. アンコール・ワット
11. プノンペン
12. アンコール・ボレイ
13. バンコク国立博物館
14.タイ中部・北部
15.チャンタブリー
付章 ビルマの仏足石
仏足石所在地リスト(タイ・ラオス)
索引
前書きなど
まえがき
仏足石は仏足跡とも日本語では書かれるが、最近のものは石(岩)に刻んだも
のだけでなく、大型化し、青銅などで作られたものが増えているため、「仏足跡」
と表記されるケースが増えてきた。英語ではBuddha('s) Footprint(s)である。本
書では「仏足石」と記述する。
仏足石はブッダが入滅後、そのお姿を形にすることは恐れ多いとして遠慮さ
れ、紀元2世紀の初めごろようやくガンダーラで仏像が作られるまでは、ブッダ
の「足型」が崇拝の対象になっていたと考えられる。足底には次第に仏教関係の
法輪などの紋様が加えられた。インドでは古来国王や聖人の足(特につま先)に額
をつけたり、接吻して「敬意を表する」習わしがあったとされる。仏足石崇拝に
はその伝統が引き継がれたものであろう。ヒンドゥー教にも足裏崇拝の跡が残
されている。ヴィシュヌ神やシヴァ神の足裏も崇拝の対象であった。これはア
ーリア系民族の習慣だともいわれる。
初期の仏足石は「足型」の上にはブッダのお姿があるものとして「両足」が信
者のほうに向けられたものが「基本」になっている。信者が足先に額をつけて崇
拝できるように便宜を図られたようである。仏像は当初はあり得なかったので、
「足型」そのものが崇拝の対象となり、インドの周辺国に広まっていった。現在
は「片足」の仏足石のほうが多くなっている。日本では中国への留学僧が転写し
持ち帰った図面をもとに我が国最初の仏足石が刻まれたのは773年とされ、それ
は奈良薬師寺に保存され、今は「国宝」に指定されているが、その後全国各地に
約300基の仏足石が存在する。
仏足石の研究では薬師寺元管長の松久保秀胤長臈が我が国における最高の権
威者であるが、氏姓学の大家として名高い丹羽基二博士も『図説世界の仏足石』
(名著出版、1992年)という労作を残されている。私は仏足石については素人研究
者であるが、タイ、マレーシア、ラオス、ミャンマーの仏足石を実際に観察した経験を多少なりとも記録にとどめたくこの書物をしたためた次第である。もちろん
対象はタイだけでも1000基を優に超えており、農村部にも拡散されており、個
人で実見できるものは少ないが、その中でも代表的なものを収録した。
私が直接ご指導いただいたのは薬師寺の松久保秀胤長臈である。松久保長臈
が拙著『シュリヴィジャヤの歴史』(めこん、2010年)をご覧になり、仏足石も調べ
たらどうかという御示唆をいただいたことが、私の仏足石調査の出発点である。
その結果、私には思いがけない発見があった。それはシュリヴィジャヤ帝国
が大乗仏教を「国教」としていたということである。シュリヴィジャヤ帝国の勢
力が広まるところ、大乗仏教も広まった。ジャワ島の「ボロブドゥール寺院」は
シャイレンドラ王朝の残した大乗仏教遺跡であるが、シャイレンドラ王国はシュ
リヴィジャヤ帝国の一部であり、それがのちに一時シュリヴィジャヤ帝国のリー
ダーになったということが判明した。