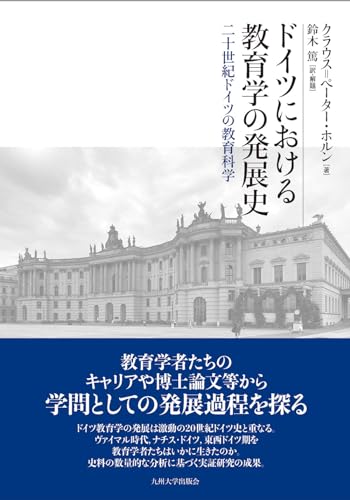目次
訳者まえがき
現在の国境線から見る各大学の所在地
第1章 導入
日本の読者に向けた解説:教授の職階について
日本の読者に向けた解説:教育学と教育科学の区別について
第2章 ヴァイマル共和国およびナチス政権期の研究大学における教育科学、1919年から1945年
1 大学所在地ごとの全体像
(1)バーデン
日本の読者に向けた解説:退職・休職の様々な形態について
(2)バイエルン
(3)ブラウンシュヴァイク
(4)ハンブルク
(5)ヘッセン
(6)メクレンブルク
(7)プロイセン
(8)ザクセン
(9)テューリンゲン
(10)ヴュルテンベルク
(11)その他の「ドイツ」大学
2 体系的分析
(1)教育科学担当のゼミナール・インスティテュート・部門
(2)出発点:1919年における教育科学担当の教授職
(3)拡大期:1920年から1932年までの教育科学担当の教授職
(4)収縮期:1933年から1945年までの教育科学担当の教授職
(5)ナチス政権期における教育科学:特異な形態(Singuläre Figuration)
(6)領域再生産と博士論文指導教員
(7)ディシプリンの発展の進展:1919年から1945年におけるディシプリンの発展傾向
(8)1944/45年の状況
第3章 ソヴィエト占領地域とドイツ民主共和国の研究大学における教育科学、1945年
から1965年
1 大学所在地ごとの全体像
(1)ベルリン
(2)ドレスデン
(3)グライフスヴァルト
日本の読者に向けた解説:新教員(Neulehrer)について
(4)ハレ-ヴィッテンベルク
(5)イェナ
(6)ライプツィヒ
(7)ポツダム
(8)ロストク
2 体系的分析
(1)1945/46年の教育科学担当の教授たち
(2)1945/46年から1955年までの教育科学担当の教授たち
(3)1956年から1965年までの教育科学担当の教授たち
(4)領域上の再生産と博士論文指導教員
(5)教授資格審査、ドイツ社会主義統一党の所属、地域主義、教育科学の内的分化:1965年までのソヴィエト占領地域ならびにドイツ民主共和国におけるディシプリン発展の傾向
第4章 西側占領地域とドイツ連邦共和国の研究大学における教育科学、1945年から1965年
1 大学所在地ごとの全体像
(1)バーデン・ヴュルテンベルク
(2)バイエルン
(3)ベルリン
(4)ハンブルク
(5)ヘッセン
(6)ニーダーザクセン
(7)ノルトライン・ヴェストファーレン
(8)ラインラント・プファルツ
(9)ザールラント
(10)シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
2 体系的分析
(1)1945年以降の「戦前期教授たち(Altprofessoren)」
(2)1945年以降の新たな着任・任用者の全体像
(3)1945/46年から1958年までの新たな教授たち
(4)付説:「科学機関拡充のための学術審議会答申(Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen)」
(5)1959年から1965年までの教育科学担当の新たな教授職
(6)ナチ党への所属、東方難民(Ostflüchtlinge)、再帰国者(Remigranten)
(7)領域の再生産と博士論文指導教員(Doktorvater)
(8)制度面・スタッフ面での自律化:1965年以前のドイツ西側地域におけるディシプリンの発展
第5章 教育科学の20世紀における制度化と地位向上、細分化と自律化
訳者解題「ドイツにおける教育学の理論発展と日本の教育学にとっての意味」
解説「学問の地盤が揺れ動くとき──教育学史研究と東西ドイツ統一」(山名 淳)
原著者あとがき
訳者あとがき
史料と引用参照文献一覧
人名索引