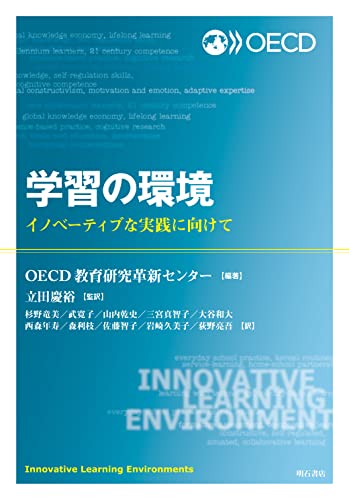目次
序文
謝辞
要旨
学習環境のコアをイノベートする
学習のリーダーシップ、デザイン、評価、そしてフィードバック
パートナーシップを通した可能性の拡張
イノベーティブな学習の原理の実行
イノベーションの生成
第1章 学習環境とイノベーティブな実践[杉野竜美/武寛子/山内乾史 訳]
はじめに
第1節 イノベーティブな学習環境の学習原理
第2節 学校効果と学校改善に関する研究による見識の構築
第3節 学習へのアプローチ
第4節 学習環境
第5節 プロジェクト事例におけるイノベーティブな実践
第6節 結論
第2章 学習環境の事例研究における学習者[三宮真智子/大谷和大 訳]
はじめに
第1節 イノベーティブな学習環境の事例研究における学習者
第2節 結論
第3章 教育のコアの要素のイノベーション[西森年寿 訳]
はじめに
第1節 学習コンテンツを再考する
第2節 学習リソースを再考する
第3節 教育者の経歴を広げる
第4節 結論
第4章 学習環境内の力学のイノベーション[森利枝 訳]
はじめに
第1節 教師のグループ再編成と教授法
第2節 学習者のグループ化
第3節 学習時間の再調整:時間の使い方のイノベーション
第4節 教授法のレパートリーの拡大
第5節 結論
第5章 形成的な学習組織のデザイン[佐藤智子 訳]
はじめに
第1節 学習リーダーシップ
第2節 教育者のリーダーシップと学習の中心性
第3節 学習者の声
第4節 形成的な学習組織が必要とする広範な学習情報
第5節 フィードバックと再デザインの重要な役割
第6節 結論
第6章 パートナーシップによる学習環境の拡大[岩崎久美子 訳]
はじめに
第1節 高等教育、企業、文化団体とのパートナーシップ
第2節 家庭や地域社会と学習環境のパートナーシップ
第3節 学習環境のネットワークを生み出すパートナーシップ
第4節 結論
第7章 「学習の本質」原理の再考[立田慶裕 訳]
はじめに
第1節 学習者中心性
第2節 学習の社会性
第3節 動機づけと感情への反応性
第4節 個人差への感受性
第5節 学習のアセスメント
第6節 水平的つながり
第7節 各原理間の相互接続
第8節 結論
第8章 イノベーティブな学習の創出と維持[荻野亮吾 訳]
第1節 イノベーティブな学習環境:ILEの枠組み
第2節 学校教育に関する基本的前提の再考
第3節 さらに前に進むために:変化の創出と維持
付録A 事例研究サイト[立田慶裕 訳]
付録B イノベーティブな学習環境の「ユニバース」と事例研究計画書(概要)[立田慶裕 訳]
監訳者あとがき
前書きなど
序文
「イノベーティブな学習環境(Innovative Learning Environments, ILE)」は、OECD教育研究革新センター(CERI)が行う国際的研究である。この研究は、青少年のための組織的学習のイノベーティブな方法に焦点を当て、学習やイノベーションに関する将来的な洞察を伴い、現代の教育改革の課題に積極的な影響をもたらす見解を提供する。ILEは、CERIの「未来の学校(Schooling forTomorrow)」研究プロジェクトの一部として始まったが、本格的なスタートに際しては学校よりも学習に焦点を当てている。同時に、周辺的なほかの方法という、よりいっそう体系的な適用へとその見解を拡張する前に、ミクロなレベルでの学習環境からまず始めることにした。
メキシコでの最初の探索的な研究は指導的な役割を果たした。この研究成果は、OECD(2008)Innovating to Learn, Learning to Innovate(邦訳『学びのイノベーション:21世紀型学習の創発モデル』有本昌弘監訳、明石書店、2016年)として刊行された。ILEの三つの段階、それ自体国際的研究として立ち上がったときに注目された三つの段階、すなわち「学習研究(Learning Research)」「イノベーティブな事例研究(Innovative Cases)」そして「実装と変化(Implementationand Change)」は、当初プロジェクトの連鎖的組織を描いていたが、これを超えるものとなっている。この研究計画は、学習組織におけるイノベーティブな変化を考察する重要な出発点が学習それ自体の深い理解にあるという信念を反映している。そこで最初の研究段階「学習研究」が、OECD(2010)TheNature of Learning: Using research to inspire practice(邦訳『学習の本質:研究の活用から実践へ』立田慶裕・平沢安政監訳、明石書店、2013年)としてまとめられた。プロジェクト計画の次の段階における主要な要素は、実践者たちがイノベーティブな学習環境のなかで実際にはどのように働いているかに集中した。それが以下に示す「イノベーティブな事例研究」である。研究に基づく原理の枠組みと学習環境の組織的な構造の枠組みを開発し、動機づけをもたらす豊かな学習イノベーションを確認したあと、もっと広い範囲での変化をもたらす戦略をどう考えるかについて、本質的な土台をこの研究はもたらした。「実装と変化」についての最後の研究は、なお進行中である。
本書は、ILE研究の第2段階、「イノベーティブな事例研究」の成果である。「学習研究」の作業が着手されたあとにこの段階が始まった。学習研究の結論が得られるかなり前に研究が始まったため、学習研究の成果から得られた十分な知識のなかで計画されたわけではない。当初から、このプロジェクトは、システムの利益やインプットへの関わり、イノベーターや政策決定者の参加を必要とした。各事例は、付録Bに示されたテンプレートの収集から始められた。一つの選択がそのテンプレートから行われると、一連のもっと詳細な事例研究が提供されるようになり、元の提案で提供されていた自己報告情報からさらに多様で分析的な詳細からなる「目録リスト(Inventory)」が作られていった。
その結果が、イノベーティブな学習環境事例の国際的な集合体である。全体で、23か国の29のシステムからなる「ユニバース」プロジェクトのなかから、125事例を本書では参考にした。もちろん、この「目録リスト」からさらに緻密な事例研究のために40の事例を選択し、その経験から本書のために核となる材料が提供され、できるかぎり元の事例研究の用語のまま説明している。この研究は、2010年から2011年にかけて行われ、2012年に最後の事例研究が終了した。各40事例のリストと詳細は付録Aに収録している。この研究活動を導くために用いられた計画書は、付録Bに要約している。探究されたイノベーティブな学習の計画や、この課題の土台となった「学習環境」の概念については、第1章で論じられている。
本書の全体的目的は、こうした広範で豊かなデータセットを公平に評価することにあった。この目的を達成するにあたり、総合化の過程で詳細な洞察を失わないようにするため、各事例から広範に編まれた抜粋を再表現する工夫を採用した。さらなる全体的目的として、この分野でよく用いられている適切な用語やツールを提供するために、「学習環境」の次元と概念の開発を行った。本書の特徴的な目的は、次の4点である。
●第一に、ILEプロジェクトを通じて提案される枠組みを精緻にして提供することである。そのために、一般的な「学習環境」と固有の「イノベーティブな学習環境」の理解が行えるようにした。両者がレポートの基本的構成のなかで述べられており、第8章で両者の点について説明されている。異なる次元を示し、両者を区別するために各事例研究の経験を活用しながら、それぞれの枠組みを発展させている。
●第二に、いかにイノベーティブな学校や学習環境がそのイノベーションを行っているかについての詳細な洞察を提供し、特に、すべての事例研究においてその考察を行えたわけではないにしろ、各事例のイノベーティブな実践について精密な注意を払っている。
●第三に、我々の力強くイノベーティブな学習環境の枠組みの中心となるILEの「学習の原理」を、現実的な事例の具体的な実践に位置づけた点である(第7章)。本研究の事例は、この求められている原理に非常に密接に適合しており、「21世紀の効果」のための基準として本書では描かれている。さらに各事例は、多様な方法でこの原理を生活にもたらしている豊かなデータベースを提供している。
●第四に、本書は、変化の重要な動因と軸を論じながら最初の二つの段階、「学習研究」と「イノベーティブな事例研究」から、第三の段階「実装と変化」への橋渡しとなっている。そこでの研究の焦点は、個別の事例からもっと広く持続的なイノベーションへと移行している(第8章)。ここには、以前OECD/CERIの研究で確認したイノベーションの四つの「原動力」の実験が含まれている。その四つとは、知識と開発研究、モジュラーの再組織、ネットワーキングとテクノロジーの進歩である。
(…後略…)