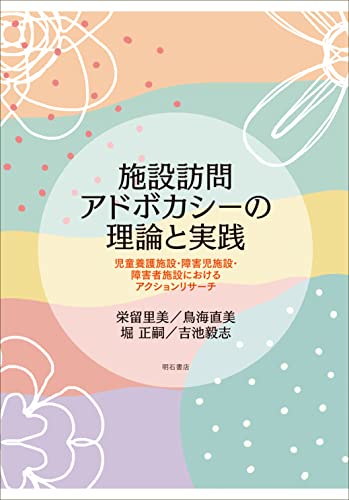目次
はじめに
第Ⅰ部 研究の概要(堀正嗣)
第1章 研究の目的・方法・展開
第2章 施設訪問アドボカシーの概要
第Ⅱ部 児童養護施設における施設訪問アドボカシー(栄留里美)
第3章 研究の背景及び研究目的
第4章 施設訪問アドボカシーの初期段階――方法模索と関係構築のステップ
第5章 個別の意見表明支援からシステムの変容に至る過程
第6章 子ども・職員による事後評価
第7章 アドボケイトによる事後評価
第8章 到達点と課題
第Ⅲ部 障害児施設における施設訪問アドボカシー(鳥海直美)
第9章 研究の背景及び研究目的
第10章 施設訪問アドボカシーの展開過程
第11章 施設訪問アドボカシーの実際――エピソード記述から
第12章 子ども・職員・アドボケイトによる事後評価
第13章 到達点と課題
第Ⅳ部 障害者施設におけるアドボカシー活動(吉池毅志)
第14章 研究の背景及び研究目的
第15章 施設訪問アドボカシーの展開過程
第16章 施設訪問アドボカシー活動の実際――エピソード記述から
第17章 施設利用者・施設職員による事後評価
第18章 アドボケイトによる事後評価
第19章 到達点と課題
第Ⅴ部 施設訪問アドボカシーの構造と意味(堀正嗣)
第20章 施設訪問アドボカシーの意義と課題――コーディネーターインタビューから
第21章 施設訪問アドボカシーの構造
第22章 障害者施設における施設訪問アドボカシーの意味――意思決定支援との関係を手がかりに
第23章 児童福祉施設における施設訪問アドボカシーの意味――意見表明支援としてのアドボカシー
第24章 施設訪問アドボカシーと地域移行支援
おわりに――コロナ下の施設訪問アドボカシーとこれから
執筆者紹介
協力機関・協力者一覧
前書きなど
はじめに
あなたが施設で生活をしていて、ルールや食事などに不満を持っていたとしましょう。忙しそうにしていたり世話になっている職員にそのことを伝えることができるでしょうか。職員から「ルールだから仕方がない」「あなただけ特別扱いはできない」と言われたり、言ったことにより面倒な人だと思われた経験がある人がいます。施設のルールだけではなく、職員や他の利用者からの暴力も同じように、「言うと余計にひどい虐待を受けるから我慢しよう」と思う人もいるかもしれません。さらに「施設から出て地域で暮らしたい」と思っても、「どうせ無理だろう」とあきらめてしまった経験がある人もいます。そんなときに、施設の外から利用者の思いを聴き、意見や意思の表明と実現を支援していく取り組みが「施設訪問アドボカシー」です。
本書は、児童養護施設・障害児施設・障害者施設で実際に施設訪問アドボカシーを実践した経験をもとに、どのような実践を行ったのか、実践の中でアドボケイトと利用者・職員の間でどのような物語が生起したのかを記述し、その意味を明らかにしています。私たちは2021年4月に、実践の成果として作成したマニュアルやツール等を中心に、『アドボカシーってなに?――施設訪問アドボカシーのはじめかた』(解放出版社)を上梓しました。本書はその姉妹編であり、前著とあわせてお読みいただければ幸いです。前著ではマニュアルやツールが中心だったのに対して、本書はアドボカシー実践の記述と分析、理論化をめざしている点に特徴があります。
私たちの実践の特徴は、子どもの施設だけでなく、おとなの施設をも対象としたことです。私たちは、この経験を通して、子どもの施設にもおとなの施設にも共通するアドボカシーの基本構造があることを認識しました。これはすべての場におけるアドボカシーに共通する土台です。一方、児童養護施設と障害児施設の違い、おとなの施設と子どもの施設の違いに基づく、アドボカシーの独自性も明らかにしました。
本来アドボカシーはすべての場で必要とされています。アドボカシーの共通基盤を土台に、高齢者施設、病院、学校など、他の分野でのアドボカシーに取り組もうと考えておられる方々にも手に取っていただけることを願っています。