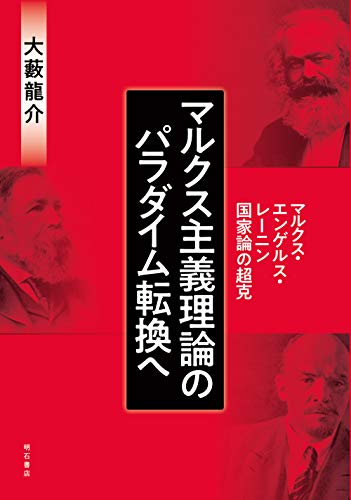目次
まえがき
Ⅰ マルクス政治理論の転回
一 フランス三部作
1 『フランスにおける階級闘争』──階級闘争史観への偏倚と革命熱望
2 『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』──意義と決定的限界
3 転換へ
4 『フランスの内乱』──第二帝制権力分析の到達点
二 イギリス政治体制の分析
1 五〇年代前半の政治的諸党派批評
2 五〇年代後半からの政治・国家体制改編の解明
3 革命路線の模索と民族問題への着目
三 プロレタリア革命論考
1 四八年革命段階の論点
2 五九年の転換──社会革命論の再定式
3 国際労働者協会の社会革命路線──協同組合型志向社会とコミューン型国家の接合
4 各国革命の多様性へのアプローチ
四 残されている課題
1 政治・国家体制研究の推移
2 果たすべくして果たしえなかった理論的課題
Ⅱ 『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』をどう読むか
一 今日までの論説
1 エンゲルス―レーニンの定説
2 異説
二 経済的階級と政治的階級 階級論的再審
1 N・プーランザス『政治権力と社会階級』の挑戦
2 政治的階級面からの照射
三 「representation 表象と代表」
1 E・W・サイード『オリエンタリズム』の事績
2 G・C・スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』の開発
3 「表象と代表」角度からの再審
四 通説反復のニューモード
1 J・メールマン『革命と反復』
2 柄谷行人「『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』」
【補】『フランスの内乱』の二、三の訳語について
Ⅲ エンゲルス国家論の地平
一 『家族、私有財産および国家の起源』の国家論の性格
二 国家発生論と国家の特徴づけ
三 国家の歴史的諸形態論
四 国家の消滅の展望
Ⅳ 十月革命におけるソヴェト国家体制創建の問題
一 二月革命
二 レーニンの革命構想
三 全ロシア・ソヴェト中央執行委員会と人民委員会議──革命政府の創成をめぐって
四 憲法制定会議解散と「勤労被搾取人民の権利宣言」──革命国家の編制をめぐって
五 党=政府による民衆革命の統轄へ
補論 十月革命の歴史的性格
Ⅴ グラムシの国家論
序
一 ファシズムの国家体制・イデオロギーとの対決
二 ヘーゲル的な国家主義的問題構成
三 国家論上の功績と欠陥
四 拡張された国家概念の射程
Ⅵ 歴史の激変のなか、ささやかな異端として──あとがきに代えて
人名索引
前書きなど
まえがき
(…前略…)
本書は、右に述べきたった思想的、理論的立場をとって、この六年程の間に発表した論攷を集成した論文集である。各論文について、次に簡単に説明する。政治・国家体制とその革命的変革をめぐるマルクスとその後継者達の理論系統を主題にして、どのように成果を吸収し限界や欠陥を突破していくか、これを眼目としている。
Ⅰ マルクス政治理論の転回
伊藤誠、田畑稔と共編の『二一世紀のマルクス』新泉社、二〇一九年、に発表の際は、紙幅の制限で大幅に縮減したので原状に復するとともに、新たに補充する加筆をおこなった。
フランス三部作、イギリス政治体制の分析、革命の展望に関するマルクスの政治理論を総攬して、その転回の軌跡を辿り、その意義、限界、残された課題を明確にした。生涯の大半にわたる力を注いだ経済学批判・『資本論』創造とは異なり、政治理論に関してはしかとした研究を遺すにいたらなかった旨を、重ねて強調した。
Ⅱ 『ブリュメール一八日』をどう読むか
『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』は、マルクスの政治理論として最も著名な論稿であり、極めて高い評価を与えられてきた。しかし、一八四八年二月革命の分析や革命の行方の展望について一面的に過ぎ、諸々の欠陥を有していた。『ブリュメール一八日』をめぐるこれまでの代表的な諸論について批評しつつ、政治的階級、「表象と代表」など、新たな角度からの多面的な批判的解読を展開した。『季報唯物論研究』第一四九号、二〇一九年一一月と第一五〇号、二〇二〇年一月に掲載した。Ⅰと併せてマルクス政治理論の決定的限界を摘示する。
Ⅲ エンゲルス国家論の地平
マルクス主義国家論の定説とされてきたエンゲルスの『家族、私有財産および国家の起源』の国家論部をはじめとした国家論の全面的な検討によって、理論的な諸難点を批判し、マルクスの国家論との相違をも明らかにする。
エンゲルス没後一〇〇年記念の杉原四郎、降旗節雄との共編『エンゲルスと現代』御茶の水書房、一九九五年、に発表した論文を再録した。論旨を明確にし、読みやすくするために、一部において表現を改め、前後の入れ替え、行替え、加筆をおこなった。
Ⅳ 十月革命におけるソヴェト国家体制創建の問題
「ロシア革命から一〇〇年─我々は何を学んだのか」特集を組んだ『季報唯物論研究』一四一号、二〇一七年一一月と一四二号、二〇一八年二月に発表した論文である。十月革命による政権奪取・人民委員会議設立から翌年一月の憲法制定会議解散・「勤労被搾取人民の権利宣言」にいたるソヴェト国家体制創建の過程と構造に焦点をあてて、従前の研究において不問であった根源的な問題として、革命政府として創設された人民委員会議は、レーニンによる「コミューン型」国家の公安委員会型国家への改竄に基づくジャコバン独裁の後進国ロシアにおける復元であり、社会主義革命としては変則的な逸脱にほかならないこと、その政府と自同化する形で構築された国家は、対立する階級や異分子の排除、権利の集団主義的制限、自由・権利に対する国家権力の優越などの構造的な歪みをもつことを析出した。また、ソヴェトに結集した労・兵・農の民衆革命とボリシェヴィキ革命の複合として実現された十月革命がボリシェヴィキ党による民衆運動の統制、圧伏へと転じていく経緯を追って、革命党を率いたレーニンの理論と実践の過誤に切り込んだ。
Ⅴ グラムシの国家論
二〇一七年四月二三日、法政大学で開かれたグラムシ没後八〇周年記念フォーラムで報告。『グラムシ没後八〇周年記念フォーラム報告集』から転載した。「国家=政治社会+市民社会」のテーゼに代表的なグラムシの国家論について、イタリアの政治的現実と思想史的伝統との関連において考察し、マルクス、エンゲルスが果たしえなかった、またレーニンに欠けていた新たな境位を開いた功績とともに反面での欠点を明らかにした。
Ⅵ 歴史の激変のなか、ささやかな異端として──あとがきに代えて
ニューレフトとして自己形成し、日本と世界の歴史が激変していくなかで、エンゲルスやレーニンのマルクス主義国家論の定説を批判しそれを超える国家論の創造を志向して苦闘を重ね、マルクス主義理論のパラダイム転換を目指すにいたった歩みを振り返った。中部大学編『アリーナ』第一九号、一九一六年、編集部からの依頼を受けて寄稿した一文。
(…後略…)