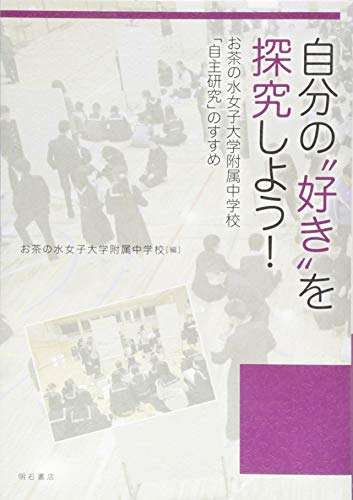目次
はじめに[加賀美常美代]
Ⅰ 自主研究の魅力[中山由美]
Ⅱ 自主研究の3年間の流れ[木村真冬]
Ⅲ 自主研究はどのように行われるか[佐藤吉高]
自主研究のいろは「課題設定・課題追究・まとめ」
〈コラム1〉遊びを中心とした幼稚園生活[杉浦真紀子・佐々木麻美]
Ⅳ お茶太郎・お茶子の自主研究[佐々木善子]
1 本研究に入るまで
2 スパイラルな学び
3 さまざまな発表の機会
〈コラム2〉「主体的・対話的で深い学び」としての自主学習[戸張純男]
Ⅴ 進化し続ける自主研究[薗部幸枝]
自主研究の歩み
自主研究を支え続けてきた同窓会(鏡影会)
〈コラム3〉「自主自律」と高等学校での実践例[佐藤健太・山川志保]
Ⅵ 自主研究発表事例のいろいろ[西平美保]
グループ内発表
ポスターセッション
講堂発表
ビジュアル凝縮ポートフォリオ
自主研究集録
Ⅶ 将来につながる自主研究――大学や社会で自主研究がいかに活かされているか[加賀美常美代]
1 中学校における関心事や取り組んだこと
2 自主研究のテーマ
3 自主研究の学びが高校、大学、社会でどのように活かされているか
4 これまでの人生を振り返って附属学校の教育やそこでの体験など自分自身の人生や価値観にどのように影響があると思うか
まとめ
〈コラム4〉好きなことを好きだと叫べる環境[三宅智之]
〈コラム5〉自らに問うて[金原凪沙]
〈コラム6〉他者を認める[戸部和久]
Ⅷ 自主研究 困ったときのQ&A[西平美保]
おわりに[加賀美常美代]
沿革
前書きなど
はじめに
(…前略…)
本書の目的は、お茶の水女子大学附属中学校の自主研究とはどのような教育プログラムか、この40年間の歩みから自主研究の蓄積を整理し、広く発信することにある。具体的には自主研究とは何か、どのように教員は生徒を指導し、生徒はどのように学ぶのか、また、将来、大学や社会でどのように活かされているのかなどを示すことである。そのことによって、お茶の水女子大学附属中学校のこれまで培ってきた教育の独自性を明確にし、広く公教育に貢献できる道筋を提示したいと考えたからである。
本書は、全8章から構成されている。まず、Ⅰ章は、自主研究の魅力とはどのようなものか例を挙げながら論じている。Ⅱ章は、中学校の3年間でどのように「自主研究」の力を育むのか、どのようなことを学び、どのように研究を進め発表にいたっているか、3年間の流れを述べている。Ⅲ章は、自主研究はどのように行われるか、自主研究のいろはを紹介している。Ⅳ章は、生徒の立場から自主研究の経験を述べている。Ⅴ章は、自主研究の歩みやこれまでの歴史を通して、その困難や紆余曲折、大学や同窓会の協力のもとで行われてきたことなどが書かれている。Ⅵ章は、生徒の自主研究の具体例を挙げ、多様な発表形態の代表的なものを表している。Ⅶ章は、附属高校・大学に進学した卒業生の自由記述から、自主研究がどのように将来に活かされているか論じている。Ⅷ章は、教師の立場から自主研究のQ&Aを挙げている。
(…後略…)