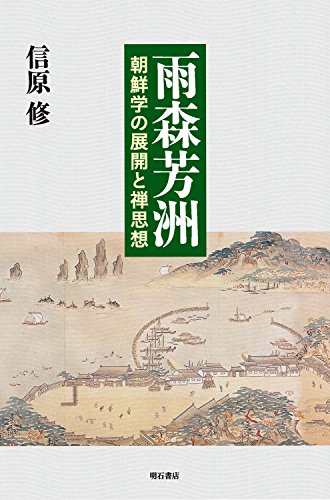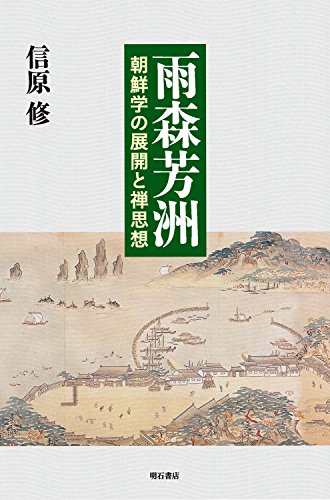目次
まえがき
第一章 中国学から朝鮮学へ――「ことば」の体現者としての芳洲
はじめに
一、芳洲の語学修業とその背景
二、芳洲の言語(習得)観
(1)音韻論的立場から見た三国語(中国・朝鮮・日本語)の違い
(2)訓読による理解は真の理解に非ず
(3)書き言葉に対する話し言葉の優先(話し言葉こそ言語の第一義)
三、『全一道人』(一七二九)にみるハングル習得のための芳洲の実践
(1)先行研究と『全一道人』執筆の背景
(2)芳洲の実践例
(3)芳洲の朝鮮語観察
Ⅰ リエゾン(liaison、連音化):終声子音の初声化
Ⅱ 同化現象(assimilation)
1.無声子音の有声化(濁音化)
2.鼻音化(nasalization)と/n/の挿入
3.流音化
Ⅲ 二点濁点と三点濁点
1.二点濁点による二種の音表記――有声音と濃音の表記として
2.多様な音価表示の三点濁点
3.音素文字と音節文字
四、芳洲の先見性と臨界年齢仮説
(1)幼児期の語学教育に対する執念
(2)臨界年齢仮説と朝鮮使節の芳洲賛嘆
五、対馬藩通詞に対する芳洲の現実認識と実情
(1)対馬における通詞養成所開設前後
(2)芳洲の通詞認識
(3)“通詞倭”のオーバーワークぶり
六、芳洲の提言と教育実践
(1)朝鮮語学習者(韓学生員)の要件
(2)芳洲の研修生(生員)支援体制と教育カリキュラムの構想
おわりに
関連年譜(外国語学習と通詞養成に関して)
第二章 「誠信堂記」(一七三〇)が語るもの――「こころ」の体現者としての芳洲
はじめに
一、芳洲による「誠信堂記」(一七三〇)
二、誠信堂と草梁庁舎
三、錦谷の草梁赴任と芳洲の倭館渡海
四、第八次正徳辛卯信使(一七一一)をめぐる紛糾
五、芳洲の公作米年限裁判使行
六、「誠信堂記」執筆の時期をめぐって
おわりに
第三章 伏流水としての禅――芳洲、三九歳の書(大阪歴史博物館所蔵)をめぐって
はじめに
一、大阪歴史博物館所蔵の芳洲の書
二、書の典拠
三、芳洲の書の真実
四、句の意義と禅のこころ
(1)『虚堂和尚語録』
(2)『槐安国語』
五、向上底(把住、平等)と向下底(放行、差別)
六、芳洲の思想性
おわりに
あとがき
初出一覧
史料・参考文献
前書きなど
まえがき
雨森芳洲(一六六八~一七五五)は、一般に鎖国期といわれる江戸期二六〇年のなかでも、開明的な文化人であり真の国際人であった。彼は元禄二年(一六八九)、二二歳のとき、師・木下順庵の推挽によって対馬藩第二一代藩主、天龍院公・宗義真に二〇人扶持、金子一〇両で仕えることとなった儒学者であったが、文禄・慶長の役後の屈折した国民感情が対馬(日本)、朝鮮双方に色濃く残る当時の国際環境の中にあって、海を隔てること僅かに五〇キロという地政学的な宿命をもつ隣国朝鮮と、よりよき交隣・通交関係を築くために、その生涯を捧げた「誠信の人」であった。のちに第二四代藩主となる宗義誠(義真の七男)がまだ幼いころ、芳洲がその教育に当たって一字ずつ字音・字義を示し、さらにそれを敷衍して次代の藩主としての心得を説いた『一字訓』(二巻)の巻頭に先ず挙げたのも、誠・信・真・実・孚という五字の「マコト」であった。
芳洲は、この隣国朝鮮を真に理解するために、多くの著作(『交隣提醒』『治要菅見』『朝鮮風俗考』『隣交始末物語・同句解』『交隣須知』『全一道人』『音読要訣』『韓学生員任用帳』『詞稽古之者仕立記録』など)を残した。これらの藩政上また学問上の貢献は測り知れない。その一方で彼は、朝鮮から派遣されてくる通信使や訳官使を介し、また対馬藩から朝鮮に送られる参判使を通して人的・文化的交流を図るとともに、家業人として対馬藩に仕える儒学者の身でありながら、自らも裁判(臨時に起用される外交折衝役)として現実の外交折衝の場でも立ち働いた。このように芳洲のはたらきは、実に八面六臂の多岐にわたる。
その意味で、雨森芳洲は、「ことば」(朝鮮学)と「こころ」(それを運用して儒教秩序の支配する一八世紀日朝の国際社会の舞台で、「誠信」のまことを生きる)の体現者として、八七年の生涯を終えるまで「実意」を貫き、「誠信」を生きた「実践」の人であった。
従って、私はこの小著のなかで、雨森芳洲というこのような人物を、外側から客観的・学問的に観察記述しようとするのではなく、いわば内側から、史(資)料に基づきながら経験的・体感的に芳洲を感じ取ろうと心がけてきたつもりである。
(…後略…)