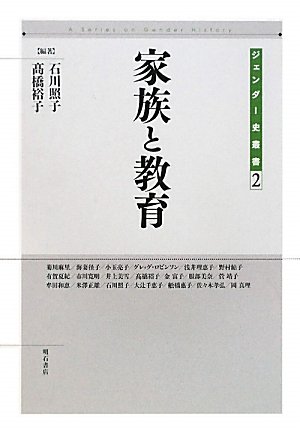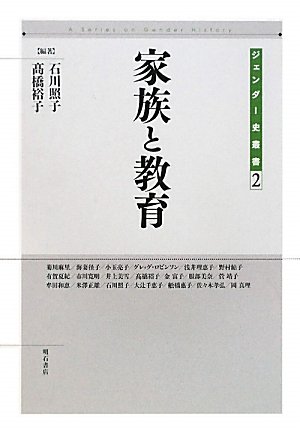目次
『ジェンダー史叢書』刊行にあたって
はじめに(高橋裕子/石川照子)
第1部 「家族」という規範とジェンダー
第1章 性モラルと家族像――イタリア近代の場合(菊川麻里)
第2章 情愛的な父親はどこにいる?――近代社会における情愛の重視と家族国家観の形成(海妻径子)
第3章 〈母の日〉が政治に現れるとき、消えるとき――昭和二三年の「祝祭日の改正」の議論から(小玉亮子)
第4章 シティズンシップの最前線――人種、シティズンシップ、そして同性婚(グレッグ・ロビンソン/浅井理恵子訳)
■コラム
烈婦の父、貞女の兄――家父長制と家族愛のあいだ(野村鮎子)
アメリカの消費文明と家族(有賀夏紀)
第2部 教育空間とジェンダー
第1章 江戸における庶民のリテラシーとジェンダー――御殿奉公と庶民の教育熱(市川寛明)
第2章 一九世紀後半のイギリスのパブリック・スクールにおける「男らしさ」(井上美雪)
第3章 津田梅子と「婦人参政権」――回顧録・伝記に省かれた事項とジェンダー規範/秩序(高橋裕子)
第4章 一九三〇年代植民地朝鮮の教育とジェンダー規範の変容――「良妻賢母」から「皇国女性」へ(金富子)
第5章 インドネシアにおけるイスラーム女子教育とジェンダー(服部美奈)
■コラム
イギリスの家庭雑誌と「女性らしさ」の表象(菅靖子)
家族国家観とジェンダー(牟田和恵)
第3部 コミュニティとジェンダー
第1章 ジェーン・アダムズはいかにしてセツルメント事業を発見・選択したのか?――女性の公的役割論の具体化過程とこれを支える思想構造に焦点をあてて(米澤正雄)
第2章 中国YWCAの家族・女性規範(石川照子)
第3章 「麻薬戦争」と女性・家族─合衆国における排除型社会の深化(大辻千恵子)
第4章 育児をめぐるジェンダー秩序――フランス、スウェーデン、日本の比較社会学的変動論(舩橋惠子)
■コラム
アメリカ合衆国南部社会におけるリンチ事件とジェンダー(佐々木孝弘)
ドキュメンタリー映画にみる、占領下パレスチナのさまざまな家族の形(岡真理)
前書きなど
はじめに
本巻では、主に近代以降の家族と教育にまつわるトピックを扱う。近代以降、家族と教育の場は、次世代と労働力の再生産に直接的にかかわる領域であり、ジェンダーによる役割分担が明示的に色分けされ、実施されることからも、ジェンダー規範がきわめて集約的に出現する空間である。家族と教育をジェンダー史として検討するということの意味はどこにあるのか。
(…中略…)
4 本巻の構成
本巻に収められている各論文は、主として近代以降のさまざまな地域における家族と教育に関するトピックを考察の対象としている。現実とのせめぎあいの中でジェンダー規範がいかに構築、再編されてきたのか、筆者たちはそれぞれの個別具体的な歴史的過程の中に、その答えを探っている。
第1部「『家族』という規範とジェンダー」では、近代以降消費と次世代を含む労働力の再生産ユニットとして、ジェンダー規範がもっとも集約的に現れている空間である家族に関して考察した論考が収められている。菊川麻里論文は、イタリア近代における性モラルと家族について、近世からの変化を踏まえてとらえている。そして女性労働者の位置づけと国勢調査の機能の分析から、母性的な女性像と性的な女性像という二律背反性を内包する産業化時代の新しい家族像の創造を指摘している。海妻径子論文と小玉亮子論文は、いずれも近代日本を対象としている。海妻論文は、近代日本におけるジェンダーの問題を、家族国家観研究の視点から分析している。具体的には男性の情愛について取り上げ、家庭よりむしろ学校や職場といった近代的職能集団が情愛充足の場となっていたことを提示している。小玉論文は、戦後の「祝祭日の改正」議論における〈母の日〉の問題を考察し、母の日制定の過程においてそれが子どもの日と接続させられてゆく中に、母の日のポリティクスを見出している。グレッグ・ロビンソン論文はアメリカにおけるシティズンシップについて、結婚に焦点を当てて検討している。異人種間結婚、婚姻法、同性婚等の考察からは、保護された地位と十全なシティズンシップという結婚の両面性が指摘されている。
第2部「教育空間とジェンダー」には、日本を含むアジアとイギリスの学校という教育空間、ならびにそこに身を置く教育者を対象として、ジェンダー視点から論じる論稿五本を所收している。市川寛明論文は、幕末から明治維新直後の東京の寺子屋・家塾における女性師匠の割合の高さに注目している。そしてそれを支えた教育熱の背景に御殿奉公が江戸庶民社会の女性の雇用先として開放されたことを指摘し、封建制そのものの規定が女性の高いリテラシーを達成させたと論じている。一九世紀後半のイギリスのパブリック・スクールの「男らしさ」を論じた井上美雪論文では、「筋肉キリスト教」を思想的根拠とするアスレティシズムと帝国主義の考察を通して、その男らしさが中流階級という集団の均一性を志向するものであったことが明らかにされている。高橋裕子論文では、津田梅子の日本の「婦人参政権」に対する立場や考え方を、回顧録や伝記の言説の分析によって解明することが試みられている。そして「婦人参政権」をめぐる政治的言動とは一線を画していたとされた津田が、実際には女性の政治的諸権利を含む社会的地位に深い関心を寄せていたこと、ただし非常に慎重に社会のジェンダー規範/秩序をずらす挑戦を行っていたことを示唆している。金富子論文は、一九三〇年代の植民地朝鮮におけるジェンダー規範の変容について、朝鮮総督府の女子教育政策を通して考察している。その結果、農村振興運動における「良妻賢母」的女性像は日中全面戦争を迎えると、戦争動員のための「皇国臣民」的女性像の育成へと転換され、朝鮮女性たちも“帝国への動員”に用いられたと指摘する。インドネシアを取り上げた服部美奈論文では、母になるための知識や教養獲得のためだけでなく、一般知識やキャリアを獲得するために女子がイスラーム学校を選択していること、しかしその教育内容には女性の地位を男性よりも下に位置づけているものも少なくないため、ジェンダー公正に向けた努力が進められていると論じられている。
第3部「コミュニティとジェンダー」では、公的領域としてのコミュニティによる社会教育や社会事業の展開、そして国家、社会と女性という問題をジェンダーの視角から論じている。米澤正雄論文は、ジェーン・アダムズがセツルメント事業を発見・選択するまでの思想形成・思想構造を検証し、カーライル思想による女性の公的役割論の追究から、後にトルストイ思想によるセツルメント事業選択へと転換する軌跡を分析している。石川照子論文で取り上げられるのは、中国YWCAが内包していた家族・女性規範である。近代中国史とジェンダーの展開を踏まえて、中国YWCAの機関誌が掲載した婚姻・教育・職業・社会変革・抗日救国運動等に関する言説を分析し、女性と国家やナショナリズムとの密接な関係性を指摘している。大辻千恵子論文ではアメリカ合衆囲の「麻薬戦争」が女性や家族に与える影響について論じられている。統計を駆使した考察からは、麻薬取締りの強化と厳罰化が特に低所得層の有色(とりわけ黒人)の女性に深刻な影響を与えていること、そして最大の犠牲者は特に黒人の子どもであるという結論が導き出されている。舩橋惠子論文は仕事と育児の両立について比較社会学の視点から検討している。未だもって仕事と育児の両立が困難な日本の状況を変革する可能性について、スウェーデン、フランスを事例として検討し、ヨーロッパ・モデルの意義と限界を指摘した上で、新しいモデルの追究を提唱している。
その他多様な地域の多彩なトピックを扱った六つのコラムもきわめて示唆に富み、本巻全体を通して個別具体的な家族、教育空間、コミュニティの歴史的文脈におけるジェンダーの構築と変容の多様性とともに、あわせて文化横断的なジェンダー規範の共通性についても理解することができると確信している。
(…後略…)