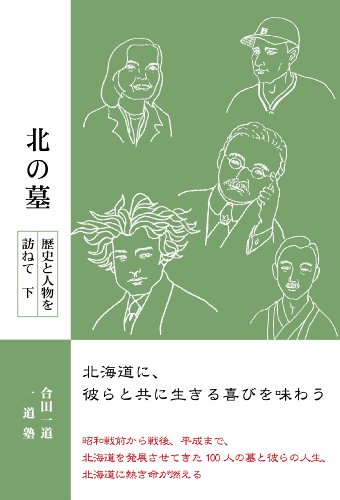目次
北の墓―歴史と人物を訪ねて 下 もくじ
この本を手にした方へ ~ はじめに 2
第一章 暗雲の昭和戦前
白虎隊士の意地花開く―丹羽五郎 12
小樽の北防波堤を建設―広井勇 15
夕陽を拝む盲目の墓守―内田徳次郎 18
灌漑工事で水田を開く―泉麟太郎 21
選挙運動の最中に急死―中西六三郎 24
フルヤのミルクキャラメル作る―古谷辰四郎 27
キリスト教のパイオニア―内村鑑三 30
北海道史の作成に尽くす―河野常吉 33
特高警察に虐殺された革命作家―小林多喜二 36
貧しい人のために遠友夜学校―新渡戸稲造 39
非行少年の更生に家庭学校―留岡幸助 42
獄死した若き天才―野呂栄太郎 45
自らの予言通りに死ぬ―三岸好太郎 48
三つのペンネームで書きまくる―長谷川海太郎 51
利益を地域振興に還元―新田長次郎 54
北海道大学の発展に尽くす―佐藤昌介 57
小説『石狩川』を上梓―本庄陸男 60
頭部に送球を受け死ぬ―久慈次郎 63
小樽の南防波堤を造る―伊藤長右衛門 66
若きプロレタリア詩人―小熊秀雄 72
弱者に医療の手を差し延べる―関場不二彦 75
口語短歌の旗手として―並木凡平 78
五百羅漢を描いた画家―林竹治郎 81
「空の軍神」と讃えられる―加藤建夫 84
出獄人の保護に尽くした先駆者―原胤昭 87
屯田人形を作り、後世へ―吉田信静 90
図書館の父と呼ばれる―岡田健蔵 93
「童謡は童心の自然詩である」―野口雨情 96
敗戦、新婚四日目に心中した夫妻―幸田明・美智子 99
第二章 揺動の戦後前半
〝開拓の母〟として生きる―渡辺カネ 108
『馬追原野』に父の労苦を描く―辻村もと子 111
植物園造り、自然保護に尽くす―宮部金吾 114
「男爵イモ」を作った男―川田龍吉 117
警官が射殺された「白鳥事件」―白鳥一雄 120
綴り方で子どもの心の成長を願う―木村文助 123
乳房よ永遠なれ―中城ふみ子 126
無国籍を貫いた大投手―ヴィクトル・スタルヒン 131
童謡「どんぐりころころ」を作る―梁田貞 134
アイヌ民族出身の北大教授―知里真志保 137
歌集「若きウタリに」を残して―バチラー八重子 140
『生れ出づる悩み』のモデル画家―木田金次郎 143
「雪は天からの手紙」の名文句残す―中谷宇吉郎 146
雪崩に埋もれ「書置」残す―沢田義一 149
『日本人の精神史研究』を執筆―亀井勝一郎 154
北海高校野球部を育てる―飛沢栄三 157
農村歌舞伎をつくる―花岡義信(大沼三四郎) 160
戊辰の敗者を視点に書く―子母沢寛 163
歌謡曲を次々にヒットさせ―万城目正 166
『雪明りの路』を著す―伊藤整 169
酒は涙かため息か―高橋掬太郎 172
身近なものを描いた農民画家―神田日勝 175
第三章 爛熟の戦後後半
病と戦い〝涙の敢闘賞〟―名寄岩静男 180
官界からマスコミに転身―阿部謙夫 183
辣腕振るい〝日魯王国〟を築く―平塚常次郎 186
甚句にも歌われた美男横綱―吉葉山潤之輔 189
北海道が生んだ初の横綱―千代の山雅信 192
断崖絶壁で測量に邁進―川村カ子ト 195
昭和新山の誕生を克明に描く―三松正夫 198
ニッカウヰスキーを作る―竹鶴政孝 201
洋裁通じ女性の意識高める―浅井淑子 204
反骨精神を貫いた彫刻家―本郷新 207
オホーツク文化を〝発掘〟―米村喜男衛 210
三七歳で道政のトップに立つ―田中敏文 213
寒地農業の推進に努める―黒沢酉蔵 216
〝阿寒の母〟と慕われて―前田光子 219
東洋一の食品コンビナート建設―太田寛一 222
日航機、御巣鷹山に衝突、死ぬ―坂本九 225
〝原野の詩人〟と呼ばれて―更科源蔵 228
初恋が「さくら貝の歌」誕生に―八洲秀章 231
コンテでほのぼのマンガ描く―おおば比呂司 234
第四章 鳴動の平成
村民に慕われたアイヌの彫刻家―砂沢ビッキ 238
北海道史研究の第一人者―高倉新一郎 241
歴史作家の頂点に立つ―井上靖 244
北の地に斬新な建築を残す―田上義也 247
シナリオ執筆、三〇〇〇本―佐々木逸郎 250
故郷函館を愛した喜劇役者―益田喜頓 253
頑固一徹、札幌時計台を守る―井上清 256
世間を震撼させた射殺魔―永山則夫 259
信仰を背景に『氷点』執筆―三浦綾子 262
地元に居続け絵筆握る―小川原脩 265
アイヌ民族初の参議院議員に―萱野茂 268
女性の地位向上に懸ける―中川イセ 271
ひたすら太鼓を打ち鳴らし―高田緑郎 274
〝挽歌ブーム〟を巻き起こす―原田康子 277
生涯に二五〇〇曲吹き込む―三橋美智也 280
サッカー室蘭を全国に轟かす―高橋正弘 283
誰もが親しめる書道を―金子?亭 286
名物先生、どろ亀さん―高橋延清 289
子どもの詩集「サイロ」を発刊―小田豊四郎 292
企業と対決した書家市長―長谷川正治 295
映画音楽を三〇八本も作曲―佐藤勝 298
「虹と雪のバラード」を作詞―河邨文一郎 301
炭鉱を愛し、書き続ける―高橋揆一郎 304
小樽運河の保存に人生を捧ぐ―峯山冨美 307
【昭和史を刻んだ墓碑】
ソ連船、猿払村沖で転覆―インデギルカ号遭難者慰霊碑 69
「みなさん、さようなら」―九人の乙女の碑 102
終戦後にソ連潜水艦が攻撃―三船遭難慰霊之碑 104
一四〇〇余人の命を奪った―洞爺丸台風海難者慰霊碑 129
横津岳に航空機激突―ばんだい号遭難者慰霊碑 152
取材に追われた日々~あとがきにかえて 310
取材協力者 312
参考文献 314
所在地別索引 318
18
前書きなど
この本を手にした方へ~はじめに
『北の墓―歴史と人物を訪ねて』の下巻をお届けします。昭和期から平成の現在までの北海道に関わった人物一〇〇人(基)を取り上げました。
内容は、昭和戦前を一つにし、戦後を二つにわけ、それに平成の四部構成にしました。掲載は亡くなった年月により分類しました。
昭和戦前では、会津藩の白虎隊士から警察署長を経て北海道に渡り、檜山管内に丹羽村(現せたな町)を拓いた丹羽五郎や、空知管内に角田村(現栗山町)を拓いた仙台藩石川家の泉麟太郎をはじめ、渡米して学業を修め、帰国後、母校・札幌農学校の教師を務めながら、貧しい人のために遠友夜学校を開いた新渡戸稲造、札幌農学校一期生で北海道大学初代学長になった佐藤昌介などがいます。また、林不忘など三つの名で丹下左膳ものやめりけんじゃっぷものを書きまくった長谷川海太郎がいます。
特筆されるのは、特高警察の拷問を受けて惨殺された小林多喜二、捕手の送球を頭部に受けて亡くなった函館太洋倶楽部の久慈次郎、それに「軍神」と讃えられた隼戦闘隊長、加藤建夫、童謡「赤い靴」を書いた野口雨情、屯田人形を製作して世に残した吉田信静などもいます。
戦後及び平成は、読者の皆さんがよく知っている方々を取り上げました。北海高校野球部を鍛え上げた監督の飛沢栄三、馬の絵を残した画家の神田日勝、大相撲の名寄岩、女流作家では「氷点」の三浦綾子、「挽歌」の原田康子、さらには二〇一四年秋のNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」の主人公の竹鶴政孝・リタ夫妻などです。
文中は敬称を略し、年代は最初に元号を、その後にカッコ書きで西暦を書きました。年齢は昭和二四年までを当時使われていた数え年とし、民法の「年齢のとなえ方に関する法律」(昭和二五年一月一日施行)に従い、昭和二五年以降を現在使われている満年齢にしました。
この本も合田一道が中心になり、道新文化センターの「一道塾」の塾生も取材、執筆に当たりました。
二〇一四年春 合田一道